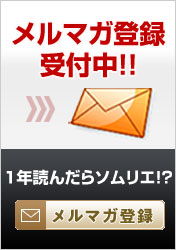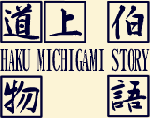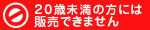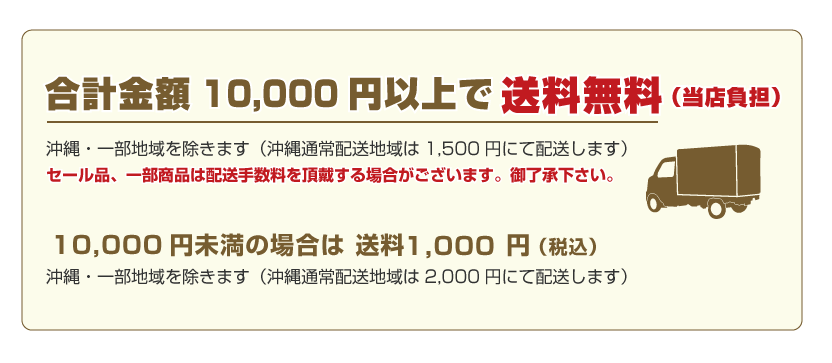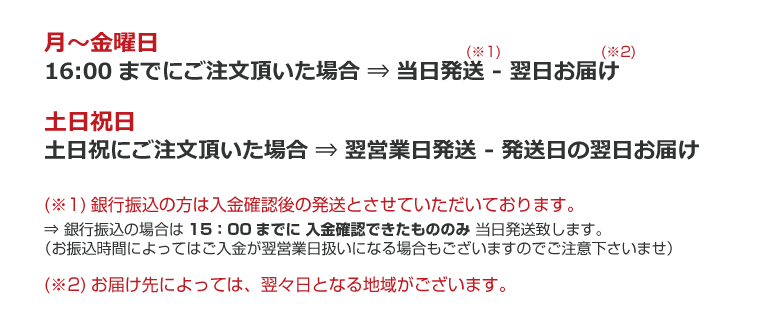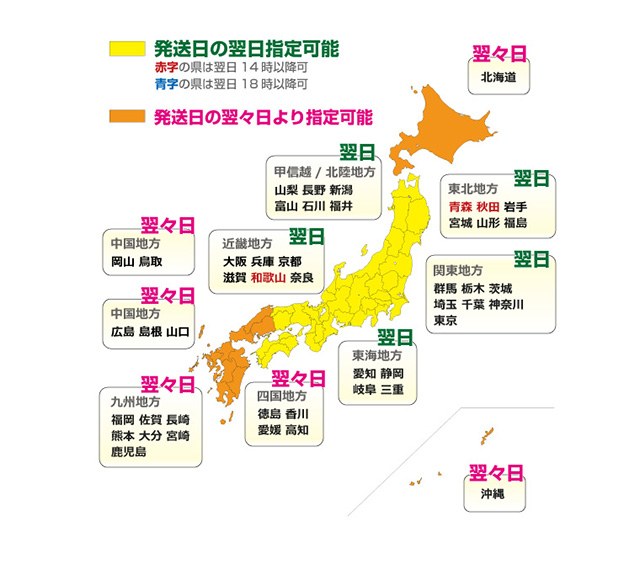ソムリエの追言「ボルドーとブルゴーニュ 」
ソムリエの追言
「ボルドーとブルゴーニュ
」
 ワインと言えば、やっぱりフランス。
ワインと言えば、やっぱりフランス。ニューワールドや国産ワインの需要が伸びている一方で、 生産量や消費量、歴史や文化をひも解いてみてもフランスが世界一のワイン大国である事は間違いないところです。
その中でも特に日本では、ボルドーとブルゴーニュはフランスの2大生産地として、 ワインの双璧のように言われていますが、実際のところはどうなのでしょう?
【ボルドー】
ボルドーはフランスの国土を五角形に見立てた場合、左下(南西部)に位置し、大西洋の影響を受けた温暖な気候と、そこを流れる大きな川に沿って発展してきました。そのため場所によって地質がまったく異なり、地域に応じた複数のぶどう品種から、幅広い味わいのワインが生産されています。そのほとんどは赤ワインで、白ワインは全体の10%程度しか作られていません。
ボルドーでは複数のぶどう品種をブレンドしてワインを作る事が多いです。 赤ワインではカベルネ・ソーヴィニヨンやメルロー、白ワインではソーヴィニヨン・ブランやセミヨンを中心に、シャトー独自の個性を打ち出しています。
昔、駆け出しの頃にお客さんの前で恰好を付けたくて、扱っていたボルドーワインのブレンド比率を丸暗記して得意満面に説明をしたのですが、 「バックラベルに書かれている割合と違うよ?」 とツッコまれて大恥をかいた経験があります。
ワインのヴィンテージが覚えていたものと違ったのです。
 シャトーではその年のぶどうの出来によって、それぞれが自分のブランドイメージを守りつつも、より品質の高い味わいに仕上がるよう毎年比率を調整しているのです。
シャトーではその年のぶどうの出来によって、それぞれが自分のブランドイメージを守りつつも、より品質の高い味わいに仕上がるよう毎年比率を調整しているのです。
そのためボルドーでは、多少天候に恵まれない年であっても、作り手達の努力によって素晴らしいワインが産みだされる可能性を秘めていると言えます。
この辺りに生産者のロマンを感じてしまうのは私だけでしょうか?
香りや味わいですが、ボルドーの赤ワインで一番多く表現される香りは、カシス。
日本ではジャムやゼリーとして売られているのをスーパーなどで見かけます。
そこを起点にさまざまな香りが生まれていきます。
カシス香は熟成を経たワインにはもちろん、比較的若いワインでも感じる事が出来ます。
メルローを主体としたワインには若いうちから楽しめるものが多いのも、ボルドーの大きな特徴の一つです。 若いうちはタンニンのどっしりとした果実味と、ヴォリューム感に溢れたパワフルな味わいが特徴です。これが熟成を経るとタンニンと色素が落ち着き、こなれたタンニンの甘み、旨みが出てきます。この円熟した味わいが、ボルドーの最大の魅力なのです。
カベルネ・ソーヴィニヨンには抗酸化作用を含むタンニンが豊富で、一般的に飲み頃は10年前後、よく作りこまれたワインになると、その飲み頃は80年後とも100年後とも言われています。
料理との相性は、やはり脂味の乗った牛肉や羊肉のステーキが一番でしょう。
どっしりとしたワインの味わいが、肉の脂と塩・胡椒の織り成す旨みと見事にマッチし、普段胸焼けして食べられないぐらいの量でも、ぺろりと食べ切れてしまいます。 他にも鶏肉、カモ肉、ジビエ(野禽類)、チーズ全般、卵料理やきのこ・・・。 ボルドーのワインは幅広い料理に合わせる事が出来ると思います。
【ブルゴーニュ】
一方ブルゴーニュは、フランスの首都パリから東南におよそ300km、マスタードで有名なディジョンから南北に広がっています。その中でも特に有名なのは、高級ワインを産出する北部のコート・ドール地区(黄金の丘の意)。ボルドーと比べると気温は低く、乾燥した大陸性気候です。
大昔は海底だったため、海からの豊富なミネラルを含んだ豊穣な土壌が広がっています。
ブルゴーニュと言えば日本では赤ワインのイメージが先行していますが、実は生産量は白ワインの方が多く、全体の6割程度作られています。赤ワインは3割、残りの1割はロゼワインとスパークリングワインです。生産量の割合からも、ヨーロッパではブルゴーニュと言えば「白ワイン」のイメージの方が強いようです。
赤ワインはピノ・ノワール、白ワインは主にシャルドネというぶどうから作られ、 ブルゴーニュでは、単一品種からワインが作られます。 畑の個性を素直に反映しやすい反面、天候などの不作年には品質を保つことが難しくなります。
赤ワインは色合いが薄く・・・薄いというとワインが水っぽいイメージに繋がるので、華やかな色合いと表現される事が多いのですが、若いうちはイチゴやバラの香りが特徴的です。 これが熟成を経て、なめし皮やジビエ香、たばこなどの熟成香へと変化していきます。
ボルドーに比べるとワインの平均寿命は短いと言えます。
 一本100万円以上の値がつくロマネ・コンティやシャンベルタンのように、濃縮した果実を得るために、ぶどうの収穫量を大幅に減らす栽培方法でも採算の取れる、一部の高級ワインメーカーを除き、一般的には10年以内には消費した方が良いとされています。
一本100万円以上の値がつくロマネ・コンティやシャンベルタンのように、濃縮した果実を得るために、ぶどうの収穫量を大幅に減らす栽培方法でも採算の取れる、一部の高級ワインメーカーを除き、一般的には10年以内には消費した方が良いとされています。
日本でブルゴーニュが流行っている理由の一つに、レストランのソムリエがやたらとブルゴーニュを勧めている影響があるように思います。和食にはブルゴーニュが合うとか、渋味が少ないからビギナーにはブルゴーニュの方が飲みやすいとか、ワインだけを楽しみたい時にはボルドーでは飲み疲れしてしまうなど色々と言われています。
道上曰く、「フランス人でそんな事を言っている人は誰もいません。
そもそもフランスと日本では食事が違うのです。
ヨーロッパでは、つまみなしにワインだけを飲む習慣が無かったのですが、
それも昔の話で、ここ10数年前からフランス人のワインの量が減り、
つまみ無しでワインを飲んでるフランス人の大半は下戸に近い方です。」との事
ワインの味わいはフルーティー、酸味が乗った繊細なニュアンスが特徴です。
個人的な意見ですが、ブルゴーニュは味わいよりも香りが高く評価されているように感じています。熟成を経た香りは、様々なものに喩えて豊かに表現されますが、味に関するコメントはあまり見かけません。「偉大」とか「官能的」とか、判で押したような言葉でどうどうと表現されていますが、味わいのコメントとしては不明瞭だと思います。
料理との相性は難しく、ワインの味わいが繊細なのでペッパーステーキなど黒胡椒の強い風味の料理には合わないので、肉料理であれば鴨肉や鶏肉のクリーム煮、豚肉料理。 どちらかと言えば素材の持ち味を活かしたあっさりとした料理の方が合うと私は思います。 牛肉に合わせるのなら、ステーキよりもタタキやカルパッチョが良いかもしれませんね。
ただしチーズに関して言えば、刺激の強いウォッシュやブルーチーズとも美味しく合わせられるので、これがまたワインの不思議なところです。
来週はさらに二つの生産地の特徴を踏まえて、色々な角度から比較してみたいと思います。
お楽しみに。
▲ページ上部へ
前号へ | 次号へ
ソムリエの追言
|