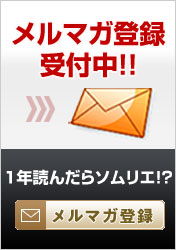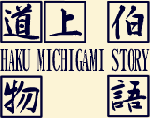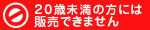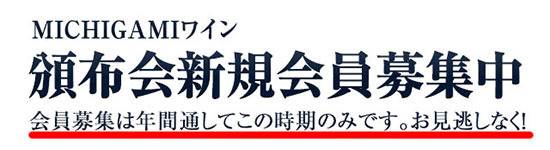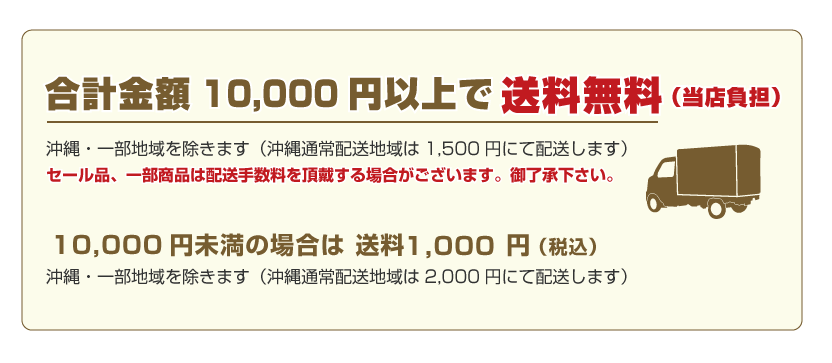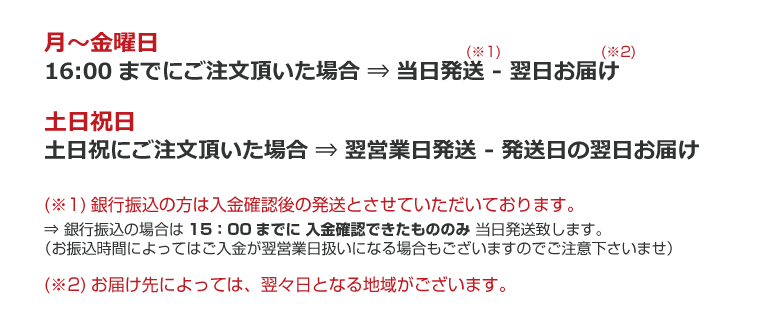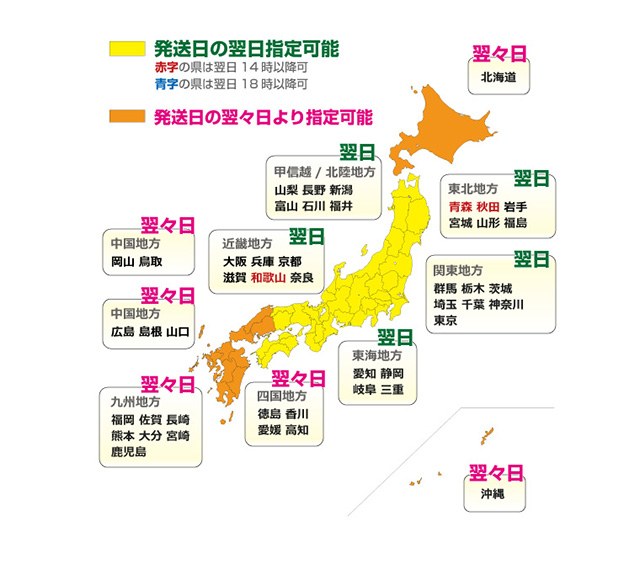ソムリエの追言「ワインの入港」
ソムリエの追言
「ワインの入港」
 MICHIGAMIワインはフランスから直接輸入をしています。
MICHIGAMIワインはフランスから直接輸入をしています。
船便で入港し,積み下ろされ税関を通過したワインは、保管倉庫へと運ばれていきます。その保管倉庫に行きワインの検品を行っています。つい先日、新たにフランスよりワインが到着しましたので行ってきました!
商品のダメージや本数の確認はもちろんですが、 一番の目的はトラックから降ろされたリーファーコンテナ(冷却・保温機能を備えた大型の貨物箱)の開封に立ち会うという事です。
長い船旅の途中で冷却機能が故障していたり、コンテナの中には錆びて穴が開き海水が入り込んでいたりする事さえあるからです。
コンテナの扉を開ける瞬間、ぴんと張り詰めた緊張が走ります。お客様の顔が浮かびます。 万が一、冷却装置が壊れていてワインに劣化がみられた場合、そのワインは安く叩き売るか処分するかの二つしかないのです。
 コンテナの二重ロックを外して重たい扉を開けると・・・暗闇の中ブゥーンというモーター音とともにひんやりとした冷気が・・・冷却装置は正常に作動しており、まずは第一段階クリアーです。
コンテナの二重ロックを外して重たい扉を開けると・・・暗闇の中ブゥーンというモーター音とともにひんやりとした冷気が・・・冷却装置は正常に作動しており、まずは第一段階クリアーです。
パレット(台木)の上には銀色の断熱シートで包まれたワインがぎっしり積み込まれています。
道上はワイン輸送の際にリーファーコンテナを使い、さらに冷却機能が故障した場合に備えて、必ずコンテナ内に断熱シートを被せるよう指示をしています。その断熱シートにも破損がないか隅々までチェックをします。
さらに、これはちょっと裏技的な方法ですが貨物船にコンテナを積み込む際には船底のスペースに置いてもらえるようお願いしているのです。 航海中に赤道直下を通過する際、船内は50℃を超える場合がありますが、海水に近い船底は温度の影響をあまり受けず、また航海中の揺れが一番少ないのです。

ワインは急激な気温の上昇に弱く、ビン内のヘッドスペース(ビン内の液面とコルクの間) の空気の体積が膨張すれば、中から押し上げる力でコルクが浮き上がったり、ワインが染み出してしまう事があります。
ワインが目減りした分、コルクと液面の間のスペースは大きくなるので、そのスペース分の空気が酸化熟成を急速させ、 ワインの劣化につながる恐れがあります。
また この液漏れによって(通称ワインが噴くと言う)ジャムっぽい香りと酸味か強まります。
 動いているフォークリフトの間をすり抜けながら、さっそく積み下ろされたワインから検品を始めていきます。
動いているフォークリフトの間をすり抜けながら、さっそく積み下ろされたワインから検品を始めていきます。 注文した通りの本数来ているか、破損やラベルの汚れ、液漏れがないかどうか。
 次に検品を終えたワインを数本、倉庫からオフィスに持ち帰って品質のチェックを行います。
次に検品を終えたワインを数本、倉庫からオフィスに持ち帰って品質のチェックを行います。一般的に、船旅などの長い移動を経てすぐのワインは、振動や揺れにより味や香りの成分が不安定な状態で、 バランスが悪くタンニンなどの収斂味を強く感じる事が有ります。
これは色素やタンニンが固形化した澱が液中に舞っているからという単純な問題だけではなく、澱の生じていない若いワイン、 白ワインやロゼワインにも同様に言われている事です。 長いワインの歴史の中で自然と生まれてきた経験則のようなものなのでしょう。
私自身、海外から到着してすぐのワインにはどこかアルコールの抜けてしまったような軽さや、 ギスギスとした強い収斂味を感じる事が多いです。
一方で道上曰く、”シャトー・タランスはボルドーで飲むとシャトー・ラ・ジョンカードより美味しいが、日本に到着してから飲むとジョンカードの方が断然美味しい。 最初、違うものを入れて送ってきたんじゃないかと怒った”と。 実はタランスは揺れに対する抵抗力のないデリケートなワインだったのです。
通常ワインはビン詰めの前にフィルターをかけて濾過するのですが、道上は苦肉の策でタランスにフィルターをかけないで日本に送ってくるように指示しました。 そうする事でやっと味わいにコクが出てくるようになったそうです。 このワインはホテル・オークラで長年愛飲されました。
昔、樽を船にのせてわざわざ揺らしてから陸に戻す事もありました。
これは、アルコール度数の高い強いワインには当てはまる出来事だということです。
すでに何百回も行っている入港作業ですが毎回、隅々までチェックをし、問題があれば細かい事でも海外の業者に直接指摘をし、改善をさせています。 時には中々受け入れてもらえない事もありますが、 より安心で美味しいワインをお届けする為に、長年の輸入経験を活かして妥協のない入港作業を行っています。
お申込みは3月一杯、年間でこの時期のみの募集となります
▲ページ上部へ