改訂版 新・スラム街の少女 ―灼熱の思いは野に消えて― 第二十一話 「第8章 臓器売買シンジケート 2」
愛は国境を越えてやってきた。
不思議な力を持つスラム街の少女プンとともに、 日本人駐在員は愛と友情をかけて、 マフィアと闘う。
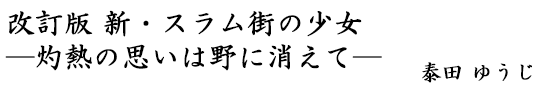
おでん屋マイでプーと偽って働いていた女性は、クンの勤めていたソイナナのカラオケ店で働いていたカノム(御菓子)だ。
アユタヤから出てきたばかりのカノムはお金が欲しかった。クンから一週間だけおでん屋マイで働いてと頼まれた。
おでん屋マイの様子を毎日電話をすれば1万バーツあげると言われた。
1万バーツもあれば、家賃も払えるし1か月の食事代にもなる。カノムは喜んで引き受けたのである。
クンから先ほど電話があり、お金をすぐに払うからスラム街の入口まで出て来いといわれ、待っていた。
シーアの運転するワンボックスカーがスラム街の入口に着くとそこにカノムが待っていた。
車から降りたクンは、カノムを車に乗るよう急き立てて、 「中でお金を払うわ、車に乗って」
クンに背中を押されるようにしてカノムは車に乗った。二人が車に乗ると車は急発進した。
「エッ、どこに行くの?お金くれるって言ったから来たのよ」
「いいところに連れてってやるよ」シーアがにやにや笑いながら言った。
黙って聞いていたカーオは、 (カノムはもう役に立たない。しかし、誘拐が実行されるまではカノムを監禁しておく必要があるだろう。
それにしてもカノムは上玉だ、シーアがほっとくわけがない。何とか手を出させないようにしよう。
シーアとは早めに手を切ろう)
車は、誘拐目的のために借りていた新しいアジトに向かって行った。
木村達が誰もいなかったクンの部屋を出て外に出ると、ビックベアとその仲間が集まっていた。
「間に合わなかった。奴らは出て行った。これを見てくれ」木村はビッグベアにカーオのメモを見せた。
「信じられない・・・・・・」ビッグベアは呟いた。
「皆、来てくれてありがとう、しばらくは様子をみよう。解散だ」
俺は事務所に意気揚揚として戻った。
「所長、心配していたんですよ。最後まで話しを聞かないで出て行ってしまうんですもの」
ふくれたアップンに、 「俺に心配という文字は必要ないよ、アップンちゃん ははは」
Vサインをしながら、カーオの書いたメモを自慢気に見せた。
アップンは不安そうに、 「所長、ま、まさかこのメモを信じているわけじゃあないですよね。
それほど馬鹿じゃあないですよね。カーオ達はあわてて出て行ったようですけど、何か手がかりが見つかりました?
何をしようとしているのか?どこに行ったのか?とか」
「大丈夫、大丈夫、心配ない、あいつら慌てて逃げて行った。まあ様子をみよう。俺が恐いんだろう。
何も起きないと思うよ」
俺は、タバコの煙で輪を作った。
「所長、探偵社からの報告の続きですが、カーオの刑務所の同房でカーオより二月前に出所した男がいます。
名前はシーアでこの男は札つきの悪で、凶暴残忍な男です。婦女暴行、傷害などの前科があります。
直近は五年前の誘拐の罪で十年の刑期でした。
なぜか減刑されて刑期の半分で出所しています」
「そいつがつるんでいるのか?」
「まだ、わかりません」
「なーんだ・・・・・・シーア?聞いたことがあるな、まあ、いっか」
アップンは、せっかくの情報を軽々しく扱われて不機嫌に、 「先ほどホテルからランチの予約の確認がありました。
ランチの内容を確認したら一番安いランチセットだったんですね、それで、時価のキャビアと良く冷えたシャンパンも用意しとくように言っときましたよ」
「・・・・・・」
その日の晩、木村は大和に立ち寄り、迷うことなくカウンターに座った。
「オッ、ちょくちょく来るようになったね、このスケベ日本人。最近カウンターにしか座らないね」ミィアオは嬉しそうに言った。
「いつも、ガツンと来るね、たまにはビールでもおごるよ。ミィアオ」
「なにか、いいことあったかな?スケベ日本人。さっき、プラーがしゃがんだ時、パンツが見えたかい」
「うっ・・・・・・」
ミィアオは、ビールの代わりにウォッカがダブル入ったスクリュードライバーを一気に飲んで木村の耳元で、 「ピンクだったね」
「いや、白のフリルだ」
「ジーっと観察していたものねえ。毛は、はみ出してなかったかい?」
「・・・・・・」
「なに、二人で話しているの?日本語わからない」
プラーがニコニコして小ママに話しかけてきた。
「あのね、木村さんたら毛が見え・・・・・・」
あわてて俺はチップを小ママに渡した。
(くそ、100バーツ紙幣と間違えて500バーツ紙幣だった・・・・・・)
「プラーの髪の毛がすてきだって。ねっ、木村さん」
「うん、あっち行ってくれる」素っ気なく言った。
プラーは小ママが席を立つと、バレンタイン17年の水割りのお代りを作って、 「日曜日、遊園地にプンちゃんと行けそう?」俺の手にそっと触れた。
「うん、大丈夫」プラーの手を握り返して言った。
「じゃあ、この前のところで待っているね」
泰田ゆうじ プロフィール 元タイ王国駐在員 著作 スラム街の少女 等 東京都新宿区生まれ |
